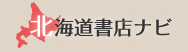北海道書店ナビ
第510回 新刊紹介 写真絵本『さくららら』

写真絵本『さくららら』を出版したアリス館は2021年で創業40周年。絵本に同封されているアリス館通信の裏一面を小寺卓矢さんが撮影した『さくららら』主人公の桜が飾っている。
[新刊紹介]
主人公は北海道朱鞠内湖畔に実在する桜の木
児童文学作家升井純子さんと写真家小寺卓矢さんの
写真絵本『さくららら』が7年越しで完成!
[2021.3.29]
「ようやく咲きました」報道に違和感
わたしが咲く日は、わたしが決める
この記事をアップする3月末、北海道の毎日はまだ雪とともにある。北海道の中でさえ雪解けのスピードは東西南北で異なり、桜の開花時期もまちまちだ。
卒業式も入学式も、年によっては春の大型連休も飛び越して、5月の薫風に花開く北国の桜。
「わたしが咲く日は、わたしが決める」
2021年3月、7年越しに完成した写真絵本『さくららら』(アリス館)は、そんな北国の桜を主人公にした物語だ。

- さくららら
升井純子 文・小寺卓矢 写真 アリス館 - 北国にある桜の木は、今年もつぼみをつけ、ふくらませ、じっくり開花の準備をする。自分の咲く日は自分で決める、さくらちゃん。それをまわりが温かく見守ります。北海道の幌加内町朱鞠内(しゅまりない)に実在するチシマザクラを主人公にした写真絵本。
企画と文章は、札幌在住の児童文学作家升井純子さん。今からさかのぼること7年前の2014年5月28日、新聞で「朱鞠内湖畔でようやく桜が開花した」という記事を読んだときのことだった。
「…”ようやく”? “ようやく”ってなんだ?って思ったんです」
南から上昇する桜前線の訪れは毎年お決まりの報道だが、それにしてもその開花の時期をとやかくは言われたくない。日本列島は細長いのだ。
「わたしが咲く日は、わたしが決める」
決め台詞がふっと浮かび、これをテーマにした初めての絵本を作ろうとテキストを書き始めた。

件の新聞記事を見せてくれる升井さん。「今となってはこの記事はわたしの宝物。よくぞ、こう書いてくれました(笑)」
このとき、升井さんがひらめいたもう一つのアイデアは「絵ではなく写真で見せる」こと。
「絵は描き手の思いどおりに描けるもの。でもこの絵本の桜はドキュメンタリータッチにしたかったんです」
その写真を撮ってくれる相方候補はこの人しかいなかった。升井家の書棚にある写真絵本『森のいのち』『だって春だもん』を手がけた北海道芽室町在住の小寺卓矢さん。
会ったことはないけれど、この人に頼みたい。思い立ったら動かずにはいられない升井さんはすぐに連絡を取り、6月、2人は札幌で初の対面を果たした。
指名を受けた小寺さん。「ぼくも升井さんが作品でいつも、子どもたちの世界を当事者目線でしっかりと描くことは知っていましたし、絵本のコンセプトを聞いたとき、いわゆる世の常識に”それ、本当?”と問い返す升井さんの反骨精神にグッときました」
第465回 児童文学作家・升井純子さんの新刊『ドーナツの歩道橋』
神奈川県出身の小寺さんは現在、北海道の森の命の営みを子どもたちに伝えたいと主に雌阿寒岳をフィールドに自然写真を撮り続け、小学校・図書館でのスライド講演も行っている。
「北海道に移住した年、ぼく自身が卒業式にも入学式にも桜がいないことに驚き、でもそのうちに、ああ、北海道には北海道の桜の咲き方があるんだよなと思うようになりました」
二人の思いが重なり、初めての共同作業が始まった。
もう一人の主人公から渡された
思い通りにならない命のバトン
主人公の桜はすぐに見つかった。そう思っていた。
升井さんと小寺さんの初対面から半年後の12月9日。小寺さんのホームグラウンドである芽室や帯広付近で桜探しを始めた二人は、廃校になった芽室町立北伏古小学校のグラウンド跡地にある一本の桜に目を止めた。
升井さんが思い描いていた「群れない一本桜で、若くて凛々しい思春期の女のコ」という条件にもほぼ合っている。
「この桜のことをわたしたちは”北伏古ちゃん”と呼んでいて、”北伏古ちゃん”が見つかった時点でわたしはすっかり、”できた!”と思いこんでいました」と升井さんは打ち明ける。
ところが、である。期待していた翌年春、北伏古ちゃんの咲きが不発に終わる。四季を通して桜の成長を描き、クライマックスは開花シーンで終わる絵本の構成を考えると、開花の写真は作品の出来を担う重要な場面だった。妥協はできない。
けれども2015年の不発に続き、2016年、2017年も思い通りの絵面が撮れなかった。当初は「できた!」と思っていた升井さんの心にも焦りがにじみ出す。
自分のペースで物語を進めていくいつもの執筆作業とは異なり、写真の上がりを待つという初めての経験にさまざまな思いが心の中で渦巻いた。
「何度も撮りに行ってくれる小寺さんに申し訳ないと思うと同時に、写真絵本づくりがこんなにも大変だったのかと自分の甘さを痛感しました」

北伏古ちゃんが主人公の時は、物語に新聞配達のおじさんや子どもたちが登場していた。
このまま北伏古ちゃんの開花を待ち続けるか、それとも次の桜を本格的に探し始めるかーー。
出版元のアリス館を含めた話し合いでは「咲かないという生き様もある。それでエンディングを迎えてもいいんじゃないか」という大胆な選択肢もあったと小寺さんは振り返る。
「咲く、咲かない、あるいは北伏古ちゃんのように咲いたとしてもどれくらい咲くかは、同じ桜の木でも毎年違うはず。その”今年は咲かないという生き様”に気づいたときに、ぼくの中で升井さんがすでに書いていた絵本のクライマックスの一文が俄然、重みを増してきた。
結論としては全国の読者に届けることを思うと、他の桜を探すという選択肢になりましたが、もともと人間の都合や期待で被写体を選ぶことは少し不遜なのではないか、という気持ちが頭の片隅にありました。北伏古ちゃんがぼくたちに教えてくれたことはすごく大きかったと思います」 人の思い通りにならないのが自然であり、命の営み。北伏古の一本桜は、今は枯れて長い眠りについている。
原点回帰で見つけた「朱鞠内ちゃん」
新たな登場人物とテキストを加えて完成
原点は「朱鞠内湖畔の桜がようやく咲いた」という新聞記事だった。「原点に帰らない?」。升井さんの言葉で現地を訪れた小寺さんから2019年5月22日、今度は升井さんのもとに朗報が届いた。「いいさくらちゃんがいる」。(今度こそ!)期待を膨らませて、翌々日、升井さんも合流した。

「見た瞬間”ようやく来たね”と言われたようで、こちらも”お待たせしました”という思いでした」(小寺さん)。
空は広く、両側に伸びている白樺がまるで桜を見守るようにそこにいる。風にのって満開のチシマザクラの花びらが舞う。
「この桜だ!」
二人とも笑顔で顔を見合わせた。
北伏古での経験から、クライマックスの開花シーンがその時点で撮れたことも二人の気持ちを軽くした。小寺さんが目ざとく見つけたウサギの糞や枯れたカタクリの葉から升井さんは新たな登場人物を書き加え、絵本づくりはいよいよ最終段階に。
2020年にかけて必要な写真を全て撮り終え、2021年3月現在、7年越しに完成した写真絵本『さくららら』は店頭で誇らしげに並んでいる。
主人公が”朱鞠内ちゃん”になり、書き加えたテキストに
こんもりとした 雪のなか
わたしは いるよ
の二行がある。小寺さんのお気に入りの文章だ。
「”わたしはいるよ”を英語にすると”Here I am”か”I exist”。この絵本自体、わたしというアインデンティティーの物語ですから、こんなにもシンプルでキレのいい文章を書ける升井さんがすごい」と作家を絶賛すると、
「それは小寺さんの写真が書かせてくれたから。これが絵だったらこうはいかなかったかもしれない。人間の言葉を引き出す写真の力を実感することができました」と升井さんも写真家を称えた。

「小寺さんには何度も”自然相手だもん、思い通りにならないよ”と言われました。相方が小寺さんで本当によかった!」

「ぼくは升井純子の文章が好きなんです。それと7年間待ってくれたアリス館の山口郁子さん、彼女の存在がなかったらこの本はできなかった」と語る小寺さん。
初のタッグは7年間の歳月を経て、北海道から全国の「わたし」を勇気づける一冊を世に送り出した。
「子どもにも大人にも、あらゆる人に読んでほしい」と声を揃える二人から、今これを読んでいるあなたにも、もう一度――。
「わたしが咲く日は、わたしが決める」

- さくららら
升井純子 文・小寺卓矢 写真 アリス館 - 北国にある桜の木は、今年もつぼみをつけ、ふくらませ、じっくり開花の準備をする。自分の咲く日は自分で決める、さくらちゃん。それをまわりが温かく見守ります。北海道の幌加内町朱鞠内(しゅまりない)に実在するチシマザクラを主人公にした写真絵本。
©2026北海道書店ナビ,ltd. All rights reserved.