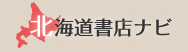北海道書店ナビ
第439回 MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店 店長 石原 聖さん
Vol.165 MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店 店長 石原 聖さん

ジュンク堂書店仙台TR店から2018年10月に現職に着任した石原店長。初北海道暮らしの感想は「いきなりの寒さがこたえました」。
[本日のフルコース]
MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店の石原店長が読む!
「論理に強くなる本」フルコース
[2019.8.26]

書店ナビ:書店員歴20年の石原店長、大阪本店や難波店、仙台TR店を見てきた目に札幌店はどう映っていますか?
石原:なんといっても多層階にわたる売り場が広い。当社のなかでも全国屈指の広さだと思います。いろいろな本が置ける強みを活かして、今後さらに品揃えを充実させていきたいです。
書店ナビ:仙台TR店で初の店長職に就任され、その前は15年間コミックのご担当だったとか。てっきり「コミック系フルコースでくるのかな」と思っていたら「論理に強くなる本」とは意外でした。
石原:手塚治虫や永井豪といった名作コミックも好きですが、同じくらい哲学や思想、論理系の本も好きなのでこちらで考えてみました。
読むのに時間がかかる本ばかりで恐縮ですが、なかなか”だし”がきいている5冊になったと思います。
[本日のフルコース]
MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店の石原店長が読む!
「論理に強くなる本」フルコース
前菜 そのテーマの導入となる読みやすい入門書

- 入門!論理学
野矢茂樹 中央公論新社 - 「正しく考える」とはどういうことか?印象をもとに意見は言えるがそれが正しいとは限らない。言葉がつくる論理には「前提が正しいなら必ず結論も正しくなる」という推論がある。そうした推論の全体を見渡すための入門書。
石原:初めからバラしてしまいますが、私が今回の5冊の中で一番最初に手に取った本が《魚料理》に選んだ野矢さんの『論理トレーニング』です。
それにハマってしまい、調べてみたらそれ以前に『入門!論理学』も書かれていることがわかり、読んでみました。
書店ナビ:日本の哲学者である野矢茂樹さんは1954年生まれ。「哲学とは、額に汗して考え抜くこと」という言葉を残した知の巨人、大森荘蔵氏に師事し、師の思索に迫る『大森荘蔵 -哲学の見本(再発見 日本の哲学)』を記す一方で、一般に向けた論理学の入門書も書いています。それが本書ですね。
中を見ると、例えば「A子は物静かだ」と形容する一方で、「A子は陰気くさい」とも形容するひとがいる。一体どちらが正しいのか、その正しさを疑う視点を持つことを教えてくれます。
石原:「物静か」も「陰気くさい」もあくまでも印象にすぎず、絶対的な評価基準というものは存在しない。これがわかってくると、もし自分が誰かに「○○さんて○○ですよね」と言われてもストレートに受け止め過ぎずにすみますよね。
ひとに言われたことが「正しい」と思い込んでしまうと、その言葉に縛られる。そこをするりとかわすためにも、本書を読んで「正しさ」って何だろうと自問する姿勢を鍛えておきたいものです。
スープ 興味や好奇心がふくらんでいくおもしろ本

- 論より詭弁 反論理的思考のすすめ
香西秀信 光文社 - 「もし人が非論理的な判断をして、それで痛くも痒くもないというのであれば、そのときは論理的思考のほうが何か大きな誤りを犯しているのである。」意見を言うとはどういうことか?正しさとは?その前提を探求した快著。
石原:これも《魚料理》の『論理トレーニング』のあとがきで野矢さんが勧めていた、という理由で読んだ一冊です。
《前菜》本で意見の正否を問う姿勢について触れましたが、こちらはそもそも「意見の正否なんて意味なくね?」という大前提で書かれています。「論理的思考力や議論の力など、所詮は弱者の当てにならない護身術である。」なんていう過激な文章も、おもしろい。
組織に所属していると、次のような場面ってありますよね。「そんな正論ばかり言ってないで、ここは○○でいかないと!」と声高に主張するひとの意見にその場がひっぱられて、しぶしぶ従わざるを得ないとか。
書店ナビ:ありますね。いま、思い当たることがひとつやふたつじゃなくてざわっとしました。
石原:理屈をこねくりまわして聞こえる”正論”よりも”言ったもの勝ち”。そういう現実社会での話し合いの流儀を知っておくことは、決してマイナスにはならないと思うんです。
書店ナビ:著者である修辞学者の香西秀信(こうざい・ひでのぶ)さんは2013年に55歳でお亡くなりになりましたが、「詭弁」や「反論」をキーワードにした著書を数冊遺されています。
SNS上を極論が飛び交う昨今こそ「反論理的思考」の正体とはどういうものなのか、しっかりおさえておきたいですね。
魚料理 このテーマにはハズせない《王道》をいただく

- 新版 論理トレーニング
野矢茂樹 産業図書 - 思考とは一種の閃きを指している。論理とは思考の結果をできる限り一貫した、飛躍の少ない、理解しやすい形で表現する。そこに論理が働く。その道筋を理解するための練習問題で構成されたのが本書。何歳からでも学びたい内容。
書店ナビ:補足しますと、本書は1997年に『論理トレーニング101題』が出版され、それをバージョン・アップして2006年に出版したのが、この『新版 論理トレーニング』になります。
石原店長はいつお読みになったんですか?
石原:ジュンク堂書店仙台TR店のときに哲学・思想系棚の担当者に勧められて手に取りました。
日常会話でたまに「あれ?なんでいきなりそういう展開(発想)になるの?」と不思議なとき、もしくは不思議がられること、ありませんか。
その「あれ?」のギャップを相手に丁寧に説明するのが論理だと思うんです。
たとえば本書の例にあるように、片手に吸いかけのタバコを持っているひとに「タバコは体に悪いからやめなよ」と言われたら、「あんたには言われたくないよ!」と反論したくなりますよね。
でもそれって実は論点のすり替えで、「タバコは体に悪い」という点では相手が言っていることが全面的に正しい。まあ、腹はたちますが。
こういう論理の道筋を各問題を解きながら自分のものにしていく本なので、とにかく読むのに時間がかかります。わたしも一年がかりで読み終え、その間何度も行きつ戻りつした記憶があります。
一筋縄ではいかない内容ですがハマったら抜けられない。やみつきになる味わいです。

取材時に特に盛り上がったのがこのページ。「PはQである」(P→Q)に始まる「逆・裏・対偶」の関係を一度徹底的に理解しておくと、「もっともらしいが実は破綻がある」論に気づくのが早くなりそうだ。
書店ナビ:ちなみにこちらが話している論点と違うことばかり返してくる相手というのは、どういう思考回路なんでしょうか。
石原:それは簡単。はなから聞く気がないんです。
肉料理 がっつりこってり。読みごたえのある決定本

- 福田恆存評論集 第五巻 批評家の手帖
福田恆存 麗澤大学出版会 - シェイクスピアの翻訳でも高名な評論家・福田恆存(ふくだ・つねあり)が巧みな論理とレトリックを駆使して、日本社会・文学・言葉について思考・表現する。副題は「言葉の機能に關する文學的考察」。
書店ナビ:福田恆存(1912~1994)は評論家・劇作家・演出家。保守派の論客として平和論・憲法問題・国語問題等を語るかたわら、演劇人としては現代演劇協会を創立し、「シェイクスピア全集」の翻訳で岸田演劇賞も受賞しています。
石原:どの評論が、ということではなく全編に渡って舌鋒鋭く、世の中のあらゆる事柄を論破する切れ味はまるで古老の剣豪よう。
読んだこちらは「切られた!」と満足げに絶命していくような読後感を味わえます。
こういう”危険人物”の本を読むのが好きなんですが、だからといってわたし自身は誰彼かまわず議論をふっかけたりはしないし、できないです。会社でももっぱら聞き役。そういうものです。
デザート スイーツでコースの余韻を楽しんで

- 議論を逃げるな 教育とは日本語
宇佐美寛 さくら社 - 元千葉大学教育学部長、宇佐美寛が不実な誤った教育言説を論破してゆく。あたかも鍛え抜かれた名剣のごとく、その言葉は明瞭でかつ重量感ある手応えを持っている。
石原:最後も”危険人物”の本になりました。《スープ》の著者、香西さんが「論争の達人」と読んだ教育学者、宇佐美寛さんの著作です。
このひとは一時期教育界でもてはやされた「アクティブ・ラーニング」という言葉の曖昧さを徹底的に論破し、本来の目的に沿った「主体的」「対話的」な「深い学び」とするべきだという自説を展開しています。
実際、「アクティブ・ラーニング」という言葉は近年すっかり聞かなくなりましたよね。もしかすると宇佐美さんの影響があるような気がします。
本書で特に痛快なのは、若い大学教員からもらった年賀はがきを見て宇佐美さんがこてんぱんにやっつける返事を出したくだり。

「本年も励みたいと思っております」という無邪気な一文が宇佐美老の逆鱗に触れた。一字一句、原文が跡形もなくなるくらいに論破したあとに「私自身は、そう気難しい男ではない。(中略)何しろ私の名は「寛」である」と書く。
書店ナビ:読んでいて「木っ端みじん」という言葉を思い出しました。そもそも、著名なことばのプロフェッショナルに、どうしてこんな社交辞令的な年賀状を出しちゃったのか…。
石原:自分から切られにいったようなものです。それは私たち読者も同じかなと。
ごちそうさまトーク 相手を敬い、自分を守る「論理力」
書店ナビ:お話をうかがっていると今回ご紹介いただいた論理本は、大学生や新社会人の方々に読んでほしいと思いました。
いわゆる「正論」と「社会の暗黙のルール」のギャップにとまどう人たちにぜひ届けたい内容です。
石原:仙台TR店ではレジ横に置いておくと、会社員風のお客様が買って行ってくれましたね。
「論理」とか「教育」と言うと四角四面な内容だと思われがちですが、実は読んでみると「社会人あるある」的なことが多かったり、宇佐美さんのようにゲキレツな視点で愚考を斬る!みたいな痛快さも詰まっている。
こういう本を読んでいると、自分が言いたいときと相手に耳を傾けるときのバランスがとれるようになったり、自分の間違いにも気づくようになる。
論理の力が自分を守る鎧になり、せわしない現代社会を疲弊せずにこぎ進んでいくオールの役目にもなると思います。
書店ナビ:自分を守り、相手を尊重するための論理。大人こそが伸ばしたい力ですね。《デザート》の後味がいつまでも舌に残る論理本フルコース、ごちそうさまでした!
MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店
2019年9月7日(土)・8日(日) 10:00~18:00
「さっぽろ出版祭り2019」開催!
市内の個性派出版社が店内にブースを出店。ワークショップもお楽しみに!
参加出版社(五十音順)
7日(土)亜璃西社、かりん舎、寿郎社、北海道大学出版会
8日(日)クルーズ、寿郎社、中西出版、柏艪舎
石原聖(いしはら・さとし)さん
新潟生まれの岡山育ち。99年にジュンク堂書店入社。大阪本店、難波店、仙台TR店等を経て2018年10月からMARUZEN&ジュンク堂書店札幌店の店長に就任。店長職の前はコミックを15年間担当した。

©2026北海道書店ナビ,ltd. All rights reserved.