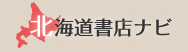北海道書店ナビ
第397回 北海道ブックフェス2018 翻訳家柴田元幸氏トークライブツアーレポート

毎年恒例、9月といえば北海道ブックフェス!
[イベントレポート]4つのトークイベントに密着!
柴田元幸さんのアメリカ文学論・翻訳術を聞く
[2018.10.15]
札幌・江別の4会場をまわる柴田元幸トークライブツアー
「まちで本と遊ぶ9月」と題して毎年9月に北海道各地でさまざまなブックイベントが開催される「北海道ブックフェス」(尾崎実帆子実行委員長)。
昨年は九州・福岡から人気書店「ブックスキューブリック」の大井実店長をゲストに迎えたトークイベントが好評を博したが、今年のゲストは河出書房新社の協力によりポール・オースターやエドワード・ゴーリーの翻訳で知られる翻訳家柴田元幸さんが来道した。
2017年の北海道ブックフェストークイベントの様子はこちら
3日間の滞在中、いずれも異なるテーマを設定した4つのトークイベントは、札幌・江別のどの会場も主催者が驚くほどの盛況ぶり!
出版翻訳業界の第一線で活躍されている柴田さんのお話を聞きたいと、北海道のアメリカ文学ファンで会場は埋め尽くされた。
以下に4会場を追いかけた当日の模様をレポートする。
1)北大図書館でアメリカ文学における「私」像を解説
柴田元幸さんのトークライブツアーは、2018年9月14日の北海道大学附属図書館からスタート。有料ながら北大関係者を中心に約80名が集まった。
この日のテーマは「アメリカ文学200年の魅力」。文学作品の主体である「私」がアメリカ文学ではどのように描かれてきたか、「アメリカ的な私」について参照文献の原文と翻訳が掲載された資料が聴講者に配布された。
柴田さんがよく通る声で音読した最初の原文テキストは19世紀に書かれたイギリス文学の『デイヴィッド・コパフィールド』と、20世紀の現代アメリカ文学『キャッチャー・イン・ザ・ライ』。
どちらも主人公の”I”(私・僕)が一人称でわが人生を語るスタイルでありながら、経歴を時系列順に理路整然と語り出すイギリス的な主人公である前者と、『ハックルベリーフィンの冒けん』の流れを受け継ぎ、感情が赴くままの口語で”You”である読者を引き込んでいくアメリカ的な主人公の違いを提示した。
この「アメリカ的な私像」は、じきに理性や道徳的な拘束から解き放たれ「自分は自分であることを言祝ぐ」流れへと発展し、アメリカを代表する詩人ウォルト・ホイットマンの『草の葉』にも、”I celebrate myself, and sing myself,”と力強くうたい上げられている。
ただし、これらの流れはマジョリティーである白人の男性著者と、マイノリティーである女性や黒人著者とでは異なる私像が立ち上るという実例も示され、聴講者は皆、熱心に聞き入った。
また、モノにあふれた消費文化が進む20世紀ともなれば、登場人物の描写が内面ではなく「あつらえのスーツを着て」「片方の腕には、(中略)ひときわ目を惹くコートを掛けている」(シオドア・ドライサー『アメリカの悲劇』より抜粋)など”持ち物”で語られる潮流が台頭したという指摘も、興味深い。
こうした話を聞き、現在の我々が生きる21世紀のアメリカ文学における私像を知りたくなるのも、当然の流れだろう。トーク後の質疑応答でも同様の質問が出た。
これに対し、柴田さんは「いま日本で最も現代アメリカ文学に精通している北大出身の翻訳家、藤井光さんからの受け売りですが」と前置きし、「現代の作家たちは自分が所属するエスニシティーや”アメリカとは”ということにも縛られていない印象。自分とは離れた別世界を臆することなく自由に描いているようです」と回答した。
2)「外へ向かう」思想を引き継いだアメリカ新聞マンガを紹介

翌日のトークツアーは、札幌と江別の2カ所で開催。午前11時、札幌市中央図書館での「アメリカ文学の歩き方・遊び方」と題したトークには、定員120名の会場に170名近くの市民が来場した。
冒頭で「今日は話がいろんな方向に広がりそうです」と予告した柴田さんの最初の話題は、英米文学の描写の違いから。
「イギリス人作家は自然の描写がうまく、アメリカ人作家は語りがうまい」例として、イギリスの作家トマス・ハーディの『萎えた腕』の一節をあげた。
主人公たちが歩くヒース(平坦な荒れ地)の描写を、「後世にはリア王の名で伝わる七世紀のウェセックス王アイナの苦難を見守ったまさにそのヒースだということも大いにありうる」と表現するあたり、「歴史と結びつけて自然を語る、すなわち自然が文明の延長上にある」と解説。
一方、柴田さんの翻訳で2017年に出版された『ハックルベリー・フィンの冒けん』からは、ハックがカヌーで霧の中をさまよう場面を引用。
「こいキリのなかにはいりこんで、どっちにすすんでるのか、死人にまけないくらいわからなくなった」というマーク・トウェイン独自の表現を、「人間にとって未知であり神秘、文明の外にある自然描写」だと指摘した。
そこからさらに、「文明の外へ出ようとするフロンティア精神を引き受けた存在」として柴田さんが紹介したのは、1900~1920年代当時の新聞マンガである。
登場人物が冒険の旅に出る、あるいは空を飛ぶといった非日常的かつファンタジーな設定や、逆さまにすると続編として読めるトリッキーな仕掛けなど、貴重な新聞マンガがスクリーンに映し出されると、見ている我々は笑ったり感心したりと大忙し。
「”外へ”と向かう意識が、雄弁な表現方法を獲得していった」と柴田さんは分析する。
質疑応答に入り、「いい翻訳とそうでもないと感じる翻訳がある」という会場からの声には「どの訳にもそれなりの必然性があると考えています」と持論を述べ、訳された時代背景や文脈を意識することが深い理解につながると補足した。
限られた時間にもかかわらず、どの質問にも丁寧に向き合っていた柴田さんだったが、次の言葉も膝を打つような説得力があり、皆さんと共有しておきたい一言だ。
「現代文学を翻訳する最大の魅力は、著者本人から直接話を聞けること。ただし、”自分が誰の影響を受けているか”という質問はタブー(レベッカ・ブラウンのような例外もいますが)。同様に”この作品で伝えようとしていることは?”という問いも、著者はそれがわからないから作品を書いているのであって、そこを考えるのは我々読者の役目だと思います」
3)ブックデザイナー時代から異彩を発揮、エドワード・ゴーリーの世界

続いて同日夕方5時半からは、トーク会場が江別に移動。読書会や古本市など本によるまちづくりが盛んな大麻銀座商店街内の「cafeもりのすみか」で、「エドワード・ゴーリー絵本の魅力」トークが開かれた。
エドワード・ゴーリー(1925年?2000年)はアメリカの絵本作家。起承転結が読めない筋立てのなか、不幸に彩られた(主に子どもが悲惨な目にあう)残酷かつシュールな世界を緻密なタッチで描き、世界中に熱狂的なファンがいる。
日本で知られるようになった発端は、河出書房新社の編集者田中優子さんが柴田さんに本邦初となる翻訳を依頼したことに遡る。
柴田さんは、個人的にも好きだったゴーリー作品を国内に紹介できるチャンスと思い、すぐに快諾したという。
記念すべき一作目は、2000 年10月に出版された『ギャシュリークラムのちびっ子たち』。AからZまでのアルファベット順に子どもたちの死が描かれるという衝撃の内容が話題を呼び、翌月刊行の『うろんな客』、翌々月の『優雅に叱責する自転車』の3冊連続刊行で一気にゴーリーファンを獲得した。

柴田さんを紹介する北海道ブックフェス実行委員長の尾崎実帆子さん
トーク当日、「cafeもりのすみか」に集まった35名の参加者の一人、学校法人北邦学園理事長の佐賀のり子さんは、小樽の絵本・児童文学研究センターに通い、幼児教育における絵本の重要性を学んでいる。
後日うかがった佐賀さんの感想が、この日の魅力を余さず言い尽くしてくれているのでそのまま引用する。
「ゴーリー作品との出会いは『おぞましい二人』、次いで『ギャシュリークラムのちびっこたち』でした。
その時の衝撃はすさまじく、子育て中であり、仕事でも日々小さな子どもたちと過ごす私にとって、それらの本はそれこそ”おぞましく不吉な”もの。
「どうしてこんな本を書くのだろう!」と憤りさえ感じるほどでしたが、同時に洗練された美しい絵やデザインに心惹かれたことも事実でした。
今回柴田元幸さんのトークに参加して、ゴーリーがブックデザイナーとしても大変素晴らしい仕事をしていたこと、タイポグラフィも自作していたことなどを知り、そのこだわりをあらためて感じました。
浮世絵からヒントを得たような絵があったり、『ギャシュリークラム』の表紙画が日本の仏像にインスパイアされているかもしれないという話も興味深く、まさにここでしか聞けないお話ばかりでした。
柴田さんが朗読したゴーリー版『赤ずきん』の絵は赤の利かせ方が素晴らしく、柴田さんの味のある声にも聞き惚れてしまいました。
全体を通して柴田さんのゴーリーに対する尊敬と愛情がはしばしから感じられて、実に気持ちのいい会でした。
ゴーリーについてちょっぴり知ることができたような、いや、さらに謎が深まったような。もっと知りたいと思う私はもう、ゴーリーの世界に引き込まれてしまったようです。
佐賀のり子
4)受講者が提出した事前課題でプロの翻訳テクニックを指導
柴田さんのトークライブツアー最終回は9月16日、札幌のかでる2・7で行われた「柴田元幸の翻訳教室~文芸翻訳のテクニック~」。
志望者は事前に提出する課題もあり、今回最も専門性の高い内容に80名を超える受講者の表情は真剣そのもの。
翻訳キャリア30年を誇る柴田さんが自分流翻訳術としてあげた5項目ーー「辞書をよく引く」「句読点を大事にする」「語順に気をつける」「読み手がどこに連れて行かれるかがわかるように文の頭を工夫する」「漢語と和語を使い分ける」ーーに、ほぼ全員がペンを動かしながら聞き入っていた。
柴田さんから事前に出されていた翻訳課題を提出した受講者は29名。
「訳のうまさが原文より前に出過ぎていないか、原文と訳が等価であるか」「”.”と”。”の使用頻度や語順が一致しているか」といった柴田さんの解説を聞きながら、受講者全員が自分がいいと思う訳に手をあげて最優秀作品を絞り込んでいく構成も、面白かった。
本企画の協力団体である文芸翻訳家養成校インターカレッジ札幌の山本基子さんの感想「札幌で柴田元幸さんの生授業を受けることができたのは、本当に幸運でした。あれだけの内容をわかりやすく1時間に納められたのは流石です。欲を言えば3時間は聴いていたかった。また来てください!」は、おそらく会場にいた全員の気持ちを代弁したものだろう。
柴田さんも「北海道の皆さんは、どの会場でもとても熱心に聞いてくださって話しがいがありました」と語る”相思相愛”のトークライブツアーであったことを、ここをご覧の皆様に胸をはってご報告したい。
なお、北海道書店ナビではトークの合間を縫って柴田さんに選書企画「本のフルコース」の取材もお願いしたところ、快く受けていただいた。
次週の更新をどうぞ、お楽しみに!
 ©島袋里美
©島袋里美
1954年東京都生まれ。アメリカ文学研究者、翻訳家。著書に『アメリカン・ナルシス』(サントリー学芸賞受賞)、『生半可な學者』(講談社エッセイ賞受賞)など多数。訳書にオースター『幽霊たち』、ピンチョン『メイスン&ディクスン』(上下、日本翻訳文化賞受賞)など多数。2017年、早稲田大学坪内逍遥大賞受賞。
次週10月22日月曜更新は、
翻訳家柴田元幸さん選書の
5冊で「いただきます!」本のフルコースです!
©2026北海道書店ナビ,ltd. All rights reserved.