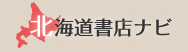北海道書店ナビ
第552回 アニメーション作家 ニヘイサリナさん
Vol.199 アニメーション作家 ニヘイサリナさん

2022年6月9日に札幌のICCで開催されたトークイベントも盛況だったニヘイさん。その場でフルコースの取材を申し込んだ。取材協力:俊カフェ
[本日のフルコース]
新進気鋭のアニメーション作家ニヘイサリナさんを形づくる
「不条理と絶望感に満ちていても生きてゆける」本フルコース
[2022.7.4]

書店ナビ:2020年に制作した7分40秒の短編アニメーション”Polka-Dot Boy”は、タイトル通り、両腕にポルカドット(同じ大きさの水玉模様)がある少年が主人公。 両親を亡くして、一人で生きているようですが、あるとき、同様のあざを持つ子どもたちをひとところに集めている集団が少年を誘拐し……。
Polka-Dot Boy (2020) – SARINA NIHEI
書店ナビ:などという説明を書いているはしから「いや、もしかしたら全然解釈違いかも…」と不安になってくる謎多き世界観で人々を魅了する本作の作者は、ニヘイサリナさん。
ロンドンのRoyal College of Artで学んだ新進気鋭のアニメーション作家で、2021年9月から札幌で制作活動を続けています。
“Polka-Dot Boy”はFest Anča 2021 Slovakiaでベストアニメ短編賞を、Bit Bang Fest 2020 Argentinaでベスト国際短編賞を受賞するなど世界の映画祭で高く評価され、日本では2020年の第7回新千歳空港国際アニメーション映画祭でも上映。
2022年6月9日に札幌のインタークロスクリエイティブセンターで開催されたトークイベントでは、他に2本のミュージックビデオ(どちらもミュージシャンから制作のオファーがあったそう)、Photay (フォテー)の”Villain (featuring golda may)”(2021/0:03:52)とTom Rosenthal(トム・ローゼンタール)の “Fenn”(2017/0:02:23)が上映されました。
フルコースをうかがう前に簡単な自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。福島県生まれのニヘイさん。中学・高校時代は映画ばかり見ているお子さんだったとか。
ニヘイ:はい、中学時代は自転車でTSUTAYAやゲオに行っては10 本くらいビデオを借りてきて、朝4時に起きて学校に行くまでに2本見る、みたいな生活を続けていました。
その頃は思春期だったこともあって自分自身を含めた世の中の全てに絶望していて、映画に救われた部分がすごくあったと思います。
あと、学校に同じようにすごく映画を見ている男子がいて、そのコに負けたくないという気持ちもありました(笑)。
書店ナビ:当時はどんな映画が心にささりましたか?
ニヘイ:特に好きだったのはキューブリック作品。あとはデイヴィッド・フィンチャーの『ゲーム』やクリストファー・ノーランの『メメント』、ミロス・フォアマンの『カッコーの巣の上で』、アレハンドロ・アメナーバルの『オープン・ユア・アイズ』やジェーン・カンピオンの『ピアノ・レッスン』、ロマン・ポランスキーの『チャイナタウン』も。
大人になってからも何度も見返しているのはゴッドファーザー3部作や『エクソシスト』です。洋画が中心でした。
書店ナビ:そんな映画三昧の中高時代を経て、大学はグラフィックデザイナーを目指して多摩美に進学したニヘイさん。そこでアニメーションの面白さに目覚めます。
ニヘイ:アニメーションの授業で片山雅博先生が世界中のいろんな作品を見せてくれたのが、大きかったと思います。私が特に好きだったのはエストニアのアニメーション。国民的作家のプリート・パルンに魅せられました。
イラストを描くのも好きでしたが、アニメーションの”動かす楽しみ”が大きくて多摩美を卒業後はロンドンの美術大学院Royal College of Artでアニメーションの修士課程を修了しました。
書店ナビ:その時の修了作品”Small People with Hats”がオタワ国際アニメーション映画祭の短編部門グランプリなど各賞を受賞し、そこからアニメーション作家としてのキャリアをスタートされました。ご本人のサイトに行くと、これまでに手がけた作品を見ることができます。
Small People with Hats – SARINA NIHEI
書店ナビ:フルコースのテーマは、ちょっとドキリとするような「不条理と絶望感」です。なぜこのテーマに?
ニヘイ:クライアントワークは別ですが、自分の作品づくりはいつも不条理だとか、底辺にいて這い上がれないような人たちが主人公です。
RCAで作った”Small People with Hats”も毎日BBCを見ていると必ず中東、シリアのニュースがメインで取り上げられていて、世界で今何が起きているのかが自分の視界に入ってくる。自分の周りにもイランから難民でイギリスに来たという知り合いがいたりして、そういう社会情勢の影響は受けていると思います。
作家としていろんな作風のものを作りたいわけではなくて、世界のどこかに「不条理と絶望感」を扱った私の作品が「深くささる」と感じてくれる人がいる。そう信じて毎回作っています。
[本日のフルコース]
新進気鋭のアニメーション作家ニヘイサリナさんを形づくる
「不条理と絶望感に満ちていても生きてゆける」本フルコース
前菜 そのテーマの導入となる読みやすい入門書

- What the Hell Are You Doing?
David Shrigley Canongate Books - イギリス人アーティスト、David Shrigley(デイヴィッド・シュリグリー)の作品集で、不条理というよりもばかばかしく笑えるアートばかりが詰まっている本。一見下手な絵柄ではあるけれど、皮肉や風刺がたくさん散りばめられたアートワークは絶望の中に可笑しみを見出すヒントをくれる。
ニヘイ:デイヴィッド・シュリグリーのことは、RCA時代に友達から教えてもらって知りました。英語で「不条理」とか「バカバカしい」という意味の”absurd”という単語があって、この人の作品はまさに皮肉たっぷりの”absurd”。
私自身もabsurdなことは皮肉でかわしていくしかないと思っていて、そういうことをずっと続けている人がいることに勇気づけられます

David Shrigleyの代表作の一つ、《I’m DEAD》。

一見グッドのように見えて《HATE》。モンティ・パイソンの国の人らしい毒がきいている。
書店ナビ:YouTubeで名前を検索すると、アニメ作品を見ることができますね。
ニヘイ:インタビューを見ると、案外まっとうなことを言ってたりするんです。でもやっぱりユーモアのセンスがあって、好きな作家さんです。
スープ 興味や好奇心がふくらんでいくおもしろ本

- 歯車
芥川龍之介 青空文庫 - 芥川の晩年の作品で、不安や絶望に満ちた物語。そこに共感して、表現者として暗黒も何か別のものに昇華する意義を考えさせられる。
書店ナビ:簡単に作品を解説しますと、「歯車」は芥川の死後に発表された遺稿の一つ。自殺直前の危機的な精神状態が生々しく描かれている私小説で、全編に死の香りが漂います。夢ともうつつともわからない描写が読者を不安に陥れます。
ニヘイ:Kindleに入れていて、ふとした時に読んでいます。自分が文章からインスピレーションを受ける作家が2人いて、それが芥川と後に出てくる太宰です。
この「歯車」は全編暗くて、不安な気持ちにさせられますが、私の場合はその不安感を思い出すために読む。こういうものを大切にしてこれまでも作ってきたし、これからも作っていかないといけないなと思い起こすために読んでいます。
芥川や太宰、それにゴッホが弟のテオに創造の苦しみを訴える手紙なんかを読むと、こんなにすごい作品を残しているひとたちでさえ、苦しみながらもなんとかやっている時期があったんだと思うと、すごく力をもらいます。
あと、太宰もそうですが、芥川は人に対して偏見が強いというか思い込みが強くて、性格が悪い(笑)。そこもささります。
魚料理 このテーマにはハズせない《王道》をいただく

- ノルウェイの森 上
村上春樹 講談社 - 生きている上で必ず訪れる絶望が、実は当たり前に存在するものだと認識した後、少しの希望が見出せる作品。
書店ナビ:1987年9月に刊行した本作は村上春樹の5作目の長編小説。ビートルズの曲を使ったキャッチーなタイトルと赤と緑を使ったクリスマスカラーの装丁があいまってこの年のベストセラーになりました。
ニヘイさんはいつ、お読みになったんですか?
ニヘイ:私が小説を読むようになったのは大学に入ってからで、2つ上の姉に勧めてもらいました。この本をきっかけに村上春樹を読むようになりましたが、主人公が自分と同じ大学生ということもあって、『ノルウェイの森』は特に共感が強い作品です。
美大は課題が多くて、毎回締め切りに追われがち。それについて行けずにだんだん大学に来なくなったコもいたので「そうはなりたくない!」と焦る自分の気持ちと、ワタナベトオルや直子たちの不安が重なったんだと思います。
今も作家として常に不安はつきもので、この気持ちは一生なくならない。それを確かめたくて読み返しているところもあります。
あと、永沢が言った「自分に同情するな」とか心に突き刺さる言葉も多かった。大学生って自分に甘くしてしまったら、どこまでも落ちていける時期なのでなおさら響いたんだと思います。
書店ナビ:出版当時は主人公を取り巻く3人の女性たち、直子とレイコ、そして緑に対して「誰に一番共感するか」「3人は主人公に対してどういう役割を果たしたのか」という議論も白熱したような記憶があります。
ニヘイ:緑の強さには憧れます。「自分もやらなきゃいけないことをちゃんとできる人間になりたい」という気持ちになる。 もう20回以上読んでいますが、今でも開いたところから夢中になって読める一冊です。
肉料理 がっつりこってり。読みごたえのある決定本

- Curtain: Poirot’s Last Case
Agatha Christie HarperCollins Publishers Ltd - アガサ・クリスティの名探偵ポワロシリーズの最終章。人が殺人を犯す理由に沸き起こる不条理感に加え、シリーズの中でも頭抜けた悲壮感と深い愛情が垣間見える作品。
書店ナビ:日本では『カーテン』のタイトルで各社から文庫本が出ています。老境に入り、体の自由もきかなくなったポワロと、妻と死別し娘のことが気がかかりなヘイスティングスが、2人が解決した初めての事件の舞台であるスタイルズ荘で再会。最後の事件に立ち向かう…。
ニヘイ:日本語版を先に読んで心にささったところを「原文ではどう書いているんだろう」と気になって、2012年3月にRCAに面接に行った時に本屋さんで原書を書いました。
それがどこか、ですか?過去にも殺人事件があったスタイルズ荘はその当時から幸せな場所などではなく、「ここには幸せな者がひとりもいない」「幸せが訪れる家ではないのだろう」とヘイスティングが気づくところ。「昔は幸せな場所だった」というのは自分の思いこみにすぎないのだと気づくくだりです。
原文も” No, none of them had been happy. And now, again, no one here was happy. Styles was not a lucky house.”で締め括られていて、なるほど、翻訳のプロってすごい!と感心しました。
ヘイスティングスは相変わらずポワロの役に立っていなくて、トンチンカンなことばかりしていますが、それも実は娘やポワロを大切に思う愛情があればこそ。すごく人間味にあふれていて、ぐっときます。

ニヘイさんが気になったもう一カ所。「あなたよりわたしのほうがずっと孤独です」という年下の女性に対して、ヘイスティングスは「あなたの人生は始まったばかりじゃないですか」「三十五で?」という会話が続く。「若くして孤独だと思って生きている人は世の中にたくさんいる、というところに共感した覚えがあります」
ニヘイ:クリスティは大学時代にハマって、古本屋さんで大人買いをしてかたっぱしから読み込んでいったほど。なぜ人が人を殺そうと思うのか、不条理な殺人事件を扱っているのに、それを一級のエンターテインメントとして昇華しているところに強く惹かれます。
私の中で、どんなに切実な絶望や不条理を描いても、最後はそれを「エンタメとして完成させたい」という思いがすごく強くて。見てくれた人に「面白かった!」だけじゃない、何か共感してもらえたり、考えさせるようなものを残せる作品を作りたい。
クリスティはその最高峰で、自分もそうありたいと思わせてくれる作家です。
デザート スイーツでコースの余韻を楽しんで

- 正義と微笑 (『パンドラの匣』収録)
太宰治 新潮社 - 太宰作品の中でもユーモアにあふれた日記調の物語で、絶望の先にどこか漠然とした楽観的思考を見出す手助けになる作品。
書店ナビ:本編は役者を目指す若き主人公の日記という体裁をとっていますが、どうやら太宰の弟子の弟、前進座に所属した堤康久さんという実在のモデルがいたことでも知られています。
太宰の性格の悪さを反映しているかのような傲慢な10代が主人公。あまりに身勝手な言い分に時折、スリッパで頭をたたいちゃいたくなる衝動に駆られました。
ニヘイ:わかります(笑)。でも自分も10代の頃はこういう人間だったなあ、という共感がものすごくて。全体を通したカラッとした明るさやコミカルさも好き。
最初の方に出てくる黒田先生の言葉もいいですよね。
日常の生活に直接役に立たないような勉強こそ、将来、君たちの人格を完成させるのだ。(中略)勉強して、それから、けろりと忘れてもいいんだ。覚えるということが大事なのではなくて、大事なのは、カルチベートされるということなんだ。
ニヘイ:それと主人公を優しく見守る兄が出てきますが、私も姉とすごく仲が良くて親友同然。尊敬しているけれど、近い関係だからこそ時にはぶつかることもある。そこにも共感しました。
主人公が劇団のオーディションで審査員に圧をかけられる場面とかは、私自身も選ばれる側の立場にいるので「ああ、あの時、こういう人いたなあ」と思い出したりもしました(笑)。
ごちそうさまトーク 「怒り」ではない何かを作りたい
書店ナビ:ロンドンから帰国後、東京を拠点にしていたニヘイさんが2021年9月から札幌暮らしを選んだのには、何かきっかけがあったんですか?
ニヘイ:新千歳空港国際アニメーション映画祭に何度も呼んでいただいたご縁で北海道に来るようになり、「いいところだな」という気持ちが高まっていったのが大きかったです。
これまでずっと人間に絶望することが多くて、その度に映画や本といった創作物に救われてきましたが、コロナ禍になり、作家同士の貴重な交流の場になっていた映画祭に行けなくなってからは、人間に救われることがすごく多かったと感じています。
でもその一方で相変わらずニュースをつければ常に子どもがひどい目にあう事件とか、どうしようもない不条理な事件ばかりが報道されている…。そういうコントロールできない世界の不条理さに、はけ口のない怒りが湧き上がってきますが、でも私自身は怒りじゃない、何か別のものを糸口にした作品を作れるのではないか、という気持ちで作っています。
書店ナビ:そこで「怒り」を選ばなかったのはどうしてでしょう。
ニヘイ:松本サリン事件で冤罪被害を受けた河野義行さんが講演会で「怒りはない」とおっしゃっているのを知って、そこに解決策があるのでないかなと感じました。
今思うと、RCAで作った”Small People with Hats”はまだ自分の中で怒りが大きい時の作品で、2020年の”Polka-Dot Boy”は自分なりの「怒りではない何か」を込めたつもりです。
怒りの連鎖は断ち切りたい。不条理を基にしながらも「怒り」に依らない何かを、これからも作っていきたいです。
書店ナビ:ニヘイさんが札幌でどんな作品を作り上げていくのかが楽しみです。「不条理と絶望感」を創作の糧に変えていく希望に満ちたフルコース、ごちそうさまでした!
ニヘイサリナさん
福島県出身。エストニアのアニメーションに魅了され、2012年に多摩美術大学グラフィックデザイン学科を卒業後、渡英し、Royal College of Artのアニメーション学科修士課程を修了。修了作品である”Small People with Hats”がオタワ国際アニメーション映画祭の短編部門グランプリを含め、数々の賞を受賞。画材はテクスチャーが気に入っているアクリル絵具を使用。抑えた色使いや無国籍風な手描きのタッチにミュージックビデオのオファーも多数。

©2026北海道書店ナビ,ltd. All rights reserved.