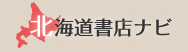北海道書店ナビ
第604回 文筆家 大洞 敦史さん
Vol.213 文筆家 大洞 敦史さん

東京生まれ・台湾在住の大洞敦史さんは日本語と中国語での文筆業のかたわら観光ガイドや通訳としても活躍。三線を弾いたり、蕎麦打ちを披露したりとマルチな活動を楽しんでいます。写真は来札した時に俊カフェで撮影。
[本日のフルコース]
台湾生活13年目の文筆家大洞敦史さんの背中を押す
「裸一貫でたくましく生きていく勇気をもらえる本」フルコース
[2024.7.8]
書店ナビ:今回は台湾とのオンライン取材でお話をうかがいました。初の著書である『台湾環島 南風のスケッチ』(書肆侃侃房)や『旅する台湾・屏東』(ウェッジ)の執筆や、Netflixで好評配信中の台湾映画『君の心に刻んだ名前』小説版や2023年に出版された『台湾 和製マジョリカタイルの記憶』などの翻訳も手がける文筆家の大洞敦史(だいどう・あつし)さんにご登場いただきます。
東京都調布市生まれの大洞さんが、台湾に関心を持つきっかけはなんだったんですか?
大洞:大学院の修士課程時代に台湾の大学との合同ワークショップがあり、それに参加したのがきっかけで好きになりました。そこから台湾各地を旅行して、一番肌に合うと感じた台南に大学院を修了してすぐに移住を決意しました。
台南は台湾の中でも早くから開発されたまちでありながら、古い建物や街並みも残っており、台北や台中と比べると素朴な田舎らしさや歴史的な情緒も感じられます。街の便利さと田舎の良さの両方がうまくミックスされていて、すごくおもしろいまちなんです。
書店ナビ:台湾は何語が話されているんですか?
大洞:主に中国語ですが、それにもいくつかありまして。中国大陸の標準語に近いものや、中国福建省の方言をルーツとする言葉です。台湾人の7割ぐらいが福建省からの移民の人たちの子孫なので。
この2つは音が全く違います。日本でいうと青森の人と鹿児島の人が地元の方言で話して、お互いに「何て言ってるんだろう?」と思うイメージかもしれませんね。
書店ナビ:そこでワーキングホリデーと日本語塾勤務を経て、現在は自営の「鶴恩翻訳社」名義でご活躍中の大洞さん。蕎麦レストラン「洞蕎麦」も5年間経営されていたとか。
大洞:私の出身地である調布市は深大寺そばが有名です。台湾にいてもふるさとの持ち味を生かしたことをやりたくて、蕎麦打ちを始めました。店はたたみましたが蕎麦打ち体験会は今も企画しています。
あとでまたお話ししますが、私は三線も弾きますのでライブイベントも開催しています。仕事とは異なるパフォーマンスの趣味を持つことも、今回のフルコースのテーマである「たくましく生きていくために」必要なことだと思っています。
[本日のフルコース]
台湾生活13年目の文筆家大洞敦史さんの背中を押す
「裸一貫でたくましく生きていく勇気をもらえる本」フルコース
前菜 そのテーマの導入となる読みやすい入門書

- ルワンダでタイ料理屋をひらく
唐渡千紗 左右社 - 東京の一流企業に勤めていたシングルマザーの著者が、当時5歳の息子と2人でアフリカはルワンダへ移住。文字通りゼロからタイ料理店を立ち上げ、開いた口がふさがらないような出来事が次から次へと続くなか、お店にも人生にも”軌道”を見出していく傑作ノンフィクション。
書店ナビ:著者の唐渡(からと)さんと大洞さんは小学校時代の同級生。大洞さんが台湾で蕎麦レストランを開業されたのが2015年11月で、その約2週間後に唐渡さんはルワンダでタイ料理屋「ASIAN KITCHEN」をオープンされたという、異国での開業経験も共有するお二人です。
本著の謝辞にも「そもそものきっかけを作ってくれた上、最後まできめ細かいアドバイスとエールを送りつつ伴走してくださった」と、大洞さんのお名前が載っています。
大洞:唐渡さんが奮闘の日々を綴っていたブログを読んで「これは絶対書籍化すべきだ!」とお世話になっている出版社の社長に強力プッシュしたんです。

唐渡さんと日本で再会したときの一枚。コロナが流行しだしてすぐ、台湾から物資不足のルワンダへマスクを送ろうとしてコンタクトをとった。
書店ナビ:開業前そして開業してからも日本社会では考えられないようなことばかりが起こり、普通はすぐに断念してしまうところですが、それをご本人が日本に一時帰国しても店がまわるくらいまでに軌道に乗せた唐渡さんのたくましさに脱帽です。
大洞:七転び八起きの意志の強さ、ですよね。それに単なる飲食店の開業物語ではなく、ルワンダの貧困やシングルマザー問題、ジェノサイドの傷跡にも言及していて、この本を通して日本とは全く異なる社会背景や価値観を持つルワンダの社会が見えてくる。いろんな意味ですごく射程の広い本になっていると思います。
なかでも特に印象的なのが、レストランスタッフのイノセントさんの存在です。ジェノサイドを経験し、子どものころから一人で生きてきた彼がコロナでルワンダ中がロックダウンした時、唐渡さんにかけた言葉は、これをご覧の皆さんにもぜひ届けたい一言です。
なお本書の出版後、唐渡さんは人生の次のステージへ踏み出すべく帰国されて、今は英語教育という新たな世界に挑戦中です。きっとうまくいくと信じています。
スープ 興味や好奇心がふくらんでいくおもしろ本

- ザ・ロード アメリカ放浪記
ジャック・ロンドン 筑摩書房 - 19世紀終盤、車掌と命がけの追いかけっこやかくれんぼをしつつ大陸横断列車にタダ乗りし、極寒や空腹に耐え、物乞いで食いつなぎ、ときには刑務所に入れられながら北米を渡り歩いたホーボー(放浪者)ジャック・ロンドン(1876~1916)の自伝。
大洞:昨年、知り合いの編集者さんがちくま文庫版を作られたのを機に買って読みました。
こういうどこにも所属せず、何も持たず、自由を謳歌しながらユーモアを持って明るく生きていく放浪者への憧憬は、マーク・トウェインしかり、チャップリンしかり、ボブ・ディランしかり、アメリカンカルチャーの根底に流れている気がします。
私自身、中学1年から不登校を選びましたので、こういう世界にすごく共感します。
書店ナビ:どこにも所属せず、何も持たず、しなやかにユーモアを持って、とは今の日本社会で相当難しい生き方かもしれません。
大洞:台湾の学校や大学で講演をさせてもらうこともあるんですが、そういうときに必ずお話しするのが「自分で足で生きていくためには3つの趣味を持ちましょう」ということです。
「3つの趣味」の1つめは外国語、できれば英語以外の外国語を習得することで、2つめはパフォーマンスできる何かを体得すること。そして3つめは、ものづくりです。
この3つがあれば自分だけでなく周りの人たちにも楽しんでもらえるし、その人たちの力になることもできる。それを突き詰めていくと、だんだん自分自身の仕事にも変化が生まれ、さらには人生を支えてくれるようになる。
私の場合は「中国語」と「三線」「蕎麦打ち」がそれらに該当し、現在の自分が台湾で自分らしく生きていくための土台になっています。
魚料理 このテーマにはハズせない《王道》をいただく

- ボクは落ちこぼれ
赤塚不二夫 ポプラ社 - ポプラ社の「のびのび人生論」シリーズは、各界の著名人が子供に向けて波乱万丈の人生を綴ったシリーズで、小学校の図書室で夢中になって読んだ。滿洲から命からがら引き揚げ、トキワ荘で漫画家を目指す赤塚不二夫の青春の日々がユーモアたっぷりに描かれている。
大洞:小学5年生ぐらいの時に読みました。当時「天才バカボン」だとか「おそ松くん」などの赤塚マンガも読んでいましたから、すごく感じるものがありました。
「ボクの、漫画の登場する子どもの考えかたや、イメージは、ほとんど、この奈良の生活によって、ボクの頭の中にはいったようだ。」(p.69)とあるように、チビ太をはじめいろんなキャラクターのモデルになった子どもたちがどんなにひどい目にあっても力強く2本の足で生きていく姿がいきいきと描かれています。
書店ナビ:赤塚さんのトキワ荘時代は”漫画の神様”手塚治虫さんがバリバリ現役で、同じ屋根の下には石森章太郎や藤子不二雄コンビ、水野英子など、のちに日本漫画の大家と呼ばれる人たちがそれぞれの才能を磨いている。
その中で自分の居場所を求めて焦り、もがく赤塚青年の姿が非常にリアルでした。
大洞:優秀な人たちが大勢いるコミュニティの中で自分自身のスタイルを打ち出していくには結局のところ、人生経験が拠り所になります。
どんなにAIやChatGPTが進んでいろんなことが瞬時にわかるようになっても、実社会の中で生きてきた経験こそが、自分自身を生かしてくれるもの。
赤塚さんのそれは、満州での戦争体験や奈良で過ごした少年時代だったのだと思います。
あと、当時強く印象に残ったのは、ところどころに赤塚さんらしい無邪気な性的エピソードが描かれているところ(笑)。そこも赤塚さんらしさ、ですね。
肉料理 がっつりこってり。読みごたえのある決定本

- ねむれ巴里
金子光晴 中央公論新社 - 1930年ごろに中国、東南アジアを経てヨーロッパを放浪した「抵抗の詩人」金子光晴(1895~1975)のパリ放浪記。自伝3部作「どくろ杯/ねむれ巴里/西ひがし」の1作。窮乏の日々を送りながら観察した人間たちのたくましさ、いやらしさ、愛らしさが他者には逆立ちしても真似できない文体で描かれている。
大洞:20代のころ、台湾を知る前にフランス文学にハマりました。語学留学で一カ月ほどパリに滞在したときはこの本を持って行き、金子さんが住んでいたモンパルナスのホテルも見に行きました。
この本は詩人が30代の時に過ごしたパリでの日々を70代になってから回想して書いたものですが、その描写が微に入り細に入り、実に細かく描かれています。
しかも舞台は陽の光が当たらない裏路地の世界で、人々はつねに貧しく、うさんくさい輩が出入りし、いつもどこかで男と女が揉めている。
そこで日本人である自分を意識しながら、”なんとかなるさ”的に生きていく著者や妻たちの生き様を呼んでいると、子どものころに大きい石ころをひっくり返してダンゴムシたちがうじゃうじゃと出てくるのをじっと観察していたのを思い出します。
それぞれは弱くて小さい存在だけれども、なんとかその場所に順応し生き抜こうともがいている。生き物本来の強い意志がうかがえます。
読めば、当時のパリの匂いも音もたちのぼる。そんな五感に強くうったえかけてくる金子さんの文体は、読むたびに「こういう文章をいつか書けるようになりたい」と思わずにいられません。
「すこし厚い敷布団ぐらいの高さしかないフランスのベッドに、からだすっぽりと埋もれて眠っているわれら同様のエトランジェたちに、僕としては、ただ眠れと言うより他のことばがない。パリは、よい夢をみるところではない。パリよ、眠れ、で、その眠りのなかに丸くなって犬ころのようにまたねむっていれば、それでいいのだ」(中公文庫版p.227より引用)
デザート スイーツでコースの余韻を楽しんで

- 山びこ学校
無着成恭編 岩波書店 - 1950年前後、山形県の山村の中学生たちが日々の生活を書きとめ、自分たちの家や村が抱える問題を探り、少しでもよくしていこうと努めた思考と実践の記録。この本から戦後社会教育の「生活綴方運動」が全国に飛び火していった。
大洞:私の修士論文のテーマは、1950年代の四日市の紡績工場における英作文サークル運動でした。工場で働く女性たちのサークル活動と、それぞれが故郷に戻ってからも文集を通して持ち続けていた繋がりについて研究しました。
この『山びこ学校』はそれと同じ文脈にあり、日本の戦後教育において「生活綴方運動」と呼ばれた作文指導の火付け役になった本です。
書店ナビ:本書の編者であり、子どもたちの先生であった無着成恭(むちゃく・せいきょう/1927~2023)さんの指導がすばらしくて、「私たちは、この三年間、ほんものの勉強をさせてもらったのです」(「答辞」p.298より)という卒業生の言葉が胸にしみました。
大洞:同感です。この本は私も日本語塾の生徒さんにプレゼントしたりして、私の中でとても大切な一冊になっています。
ごちそうさまトーク 「君はひとり立ちできる」作文教室での教え
書店ナビ:大洞さんが中学1年生で不登校になったお話を聞いてもいいでしょうか。
大洞:ええ。自分の中に”明日学校に行こうか、行くまいか”みたいな葛藤はほとんどなくて、ほぼ即決でした。
中学受験した中高一貫の男子校が電車3本を乗り換え、最寄り駅からスクールバスに乗り、さらに坂道を15分歩いて着くところにあり、毎日これを繰り返すのは人生の無駄だなと(笑)。夏休みのあとはもう学校に行かなくなりました。
それともう一つ、学校や組織に縛られず一人で生きていく道に背中を押してくれたのが、父親に勧められて小学5年の時から通っていた作文教室の存在です。
神保町で宮川俊彦さんという、国語教育界の一匹狼みたいな方が開いていた教室でした。
書店ナビ:教室では何について作文を書くんですか。
大洞:昔話を教材にするんです。「浦島太郎」とか「桃太郎」とか、そういう短いテキストを宮川さんが「これを人間の社会に置き換えると…」みたいに毎回分析していくんですね。
何通りもの解釈を通して、生徒は小学生の頃から「当たり前を疑う」という視点を持ち、テキスト読解力や分析・批評の力を育んでいく。そういう教室でした。
私はそこで宮川さんから「君は一人で生きていける才能があるから、自分の拠点を持って社会に発信していきなさい」みたいなことをコンコンと言われて育ち、「なるほど。自分はひとり立ちしても強く生きていけるんだ!」という何の根拠もない自信を持つにいたりました(笑)。
書店ナビ:少年時代にそう言ってくれる大人と出会えたことは、とても大きいですね。
大洞:そう思います。子どものころから自信が持てるか持てないかで、人生は180度変わりますよね。
私も今年の7月で40歳になりますので、これからはもっと自分を縛りつけているものを削ぎ落として、自分がやるべきことに集中して生きていきたいと思っています。
その”やるべきこと”の一つには、台湾の学生たちに「元気と自信と人生の希望、それから世界への関心。この4つを持って生きていってもらいたい」というメッセージを伝えることも入っています。それを私に教えてくれたのが、今回ご紹介した5冊でした。
書店ナビ:もうすぐ札幌と東京で大洞さん主催のイベントが開催されます。札幌の会場は俊カフェさんです。台湾に関心をお持ちの方は、ぜひお運びください。

7月19日(金)12~19時には東京・下北沢のレンタルスペース霞月坊(かげつぼう)で開催。詳細は大洞さんのブログ「素描南風」https://nan-feng.blogspot.com/をチェック!
書店ナビ:「3つの趣味」や最後に出てきた「4つの心得」など、たくましく生きるための人生の知恵が詰まった台湾からのフルコース、ごちそうさまでした!
大洞敦史(だいどう・あつし)さん
1984年東京生まれ。明治大学理工学研究科修士課程修了。2012年台南市に移住。「鶴恩翻訳社」代表。文筆家、三線奏者、蕎麦職人、台湾政府認定観光ガイド、法廷通訳者、台南市日本人協会副理事長。
©2024北海道書店ナビ,ltd. All rights reserved.